| |
||
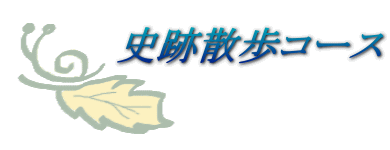 |
今日は海にまつわる数多くの史跡の中のごく一部、津田山に沿ったコースをご紹介します。
1 2 3 4 5 6 7 文字をクリックして頂くと目的の場所に飛びます
1首なし地蔵
津田西町と県道120号線が交差した三角地に祀られています。
昔、夜道を歩いてお地蔵さんの前まで来ると、お地蔵さんの首がコロリと落ちて、ころころ足元で転げまわるのだそうです。
これは狸が祀ってある「食べ物を目当て」に毎晩出てきて、人を脅かしているのだと気付き、住民が修理してお堂を建て、供養してから、二度と首が落ちることも、人を化かすこともなくなった、といわれています。
2穴観音
紀伊水道を一望できる津田山の一角に、小さな洞窟があり、その中に優しい眼差しで微笑みかけてくれる石仏が安置されています。
「穴観音」の、観音さまは如意輪観音像で、台座には、「天保14年5月18日 当浦女人講」と刻まれています。津田浦の漁師のおかみさん達が海で働く男達の安全を祈願し、安置されたものです。
又、ここは阿波狸の総大将六右衛門の根城でした。
穴観音入口穴観音の由来
「海長山穴観音」といって、霊験あらたかな観音様をまつってあり、伝説「阿波の狸合戦」の勇将六右衛門狸の本拠地である。
天保の頃、六右衛門は阿波狸界の総帥として羽振りを利かせていた。
修行中の弟子、小松島日開野の新進気鋭の「金長狸」をわが娘「鹿の子」の婿養子とし、跡目を継がせようとしたが受け入れられず、六右衛門はこれに奇襲をかけて打ち破り、金長は危うく逃げのびた。
その後多数の味方を得た金長は六右衛門と対決することになり、千代が丸、勝浦川原、津田浦一帯で大合戦を展開した。
阿波国内外の諸狸はそれぞれ、この両将に味方して、総勢600余匹、一晩中死闘を続け、屍累々として目を覆うばかりであった。
六右衛門は一敗地にまみれて討死し、金長もまた戦傷のためまもなく死亡した。
のち、それぞれの代になって和睦をした。
この合戦の際、両将に加勢した主な狸は、佐古の庚申新八、妙長寺のお睦、臨江寺のお松、高洲の隠元、淡路の柴右衛門、屋島の八毛狸などであったという。
紹介文は、案内板を引用させていただきました。
入口に立つ六右衛門狸
穴の奥には如意輪観音が奉られています
3山瀬佐蔵の墓
山瀬佐蔵は、幕末藩を代表する測量技術者で県内地図を作成しました。
17歳で阿波藩測量方、岡崎三蔵の助手となり、22歳で測量方下役、名字帯刀御免となります。
伊能忠敬が日本全図作成のため阿波に来た時、岡崎三蔵と共に助手を勤め、自分の技術向上につとめました。
文政17年(1828年)、淡路を除く阿波517村全地図を完成。
弘化初年(1844年)には淡路の地図も完成しました。出来栄えは驚くほど精密だったといいます。
文久2年(1844年)76歳で死去。お墓は津田墓地の穴観音の前にあります。
(山の麓、煙の立っているところ)
山瀬佐蔵墓誌 墓地
4山の神の祠
津田山を支配する女神で、津田西町の北向き地蔵 から小道を山裾に向かって行くと、閑静な場所に古 い榎があり、その老木の下に小さな祠が建っています。
「山の神(大山祇命)」を祀った神聖な地で、昔は山仕事を始める前に必ず、山の神にお供え物をおまつりして、おはらいを済ませてから山仕事にかかったそうです。
5津田八幡神社と津田寺境内
八幡神社の広い境内には、たくさんの史跡が残されています。 その中のいくつかをご紹介します。
津田八幡神社 津田寺
「百度石」と「千度石」
八幡神社の鳥居をくぐると、参道に「百度石」と「千度石」が並んでいるのが、まず目に入ります。
「百度石」は各地のお宮やお寺にありますが、「千度石」は珍しいものです。
船が遭難して安否を気遣い素足になって百度石に、大掛かりなことがおきたときは、願いを込めて千度参りをして、奇跡を神仏にすがったといわれています。
本殿左に「数取り板」があり、当時が偲ばれます。百度石と千度石 数取り板
大楠と楠大明神
「楠大明神」(一名お六大明神)
境内には推定樹齢5〜600年の大楠が繁り、 徳島市の保存樹木 に指定されています。
大楠の横には「楠大明神」という狸の祠があります。商売繁盛成績向上に霊験あらたかとかで参詣者も多いようです。
「津田小学校発祥の地」
明治6年3月1日(1873年)、津田寺観音寺堂を校舎に「化成校」(よく育て成長させる意)として創立されました。
創立時は、教員2名、児童数60名であったといいます。
現在の地に建物ができたのは昭和11年だそうです。
「権右ヱ門大明神」
権右ヱ門大明神は有名な阿波狸合戦では信義を重んじて、六右衛門方の大将として、奮戦し、戦死したそうです。
生前は津田寺の本堂下に住み、時の住職に可愛がられました。
家内安全・商売繁盛・交通安全・入学試験など所願成就に霊験があるそうです。
この他、境内には江戸積み回船の海上安全を祈願した石柱とか、珍しい狛犬さん・子安地蔵・青面観音・住吉神社・船玉神社などまだまだ多くの名所旧跡があります。
6水神社
岩の鼻の断崖の下に建つ水神さんは、津田島の起点に祀られ、航海の安全を祈ったものでした。
大正年間、地元の有志によって、今の本堂や鳥居が建てられ、毎年5月には沖行司(漁業者)により、祀られています。
境内の榎の大木は(県下7番目)だとか。
7岩の鼻
ここは津田のシンボル的な断崖です。昔、津田島の往来の起点は岩の鼻でした。
江戸時代文化年間(1810年頃)まで、この岩に波が打ちかけ、干潮時には、麓の岩づたいに渡し場(西裏川)に出て、渡し舟で南斎田に渡っていました。
なおご紹介にあたり、津田新浜地区青少年健全育成協議会発行の「ふるさとマップ」を参考資料に使わせていただきました。