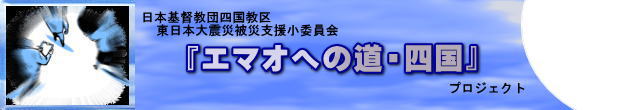
|
第二次 震災ボランティアの報告 |
|||
| 丸亀教会主任担任教師 岡田真希 | |||
| 皆様のご支援をいただき、2011年10月17~21日の5日間、仙台・石巻に行かせていただきました。参加メンバーは、岡田真希(丸亀教会主任担任教師)、 岡田・西村が石巻で、 |
|||
|
10月17日 丸亀より仙台へと新幹線で移動。東北教区センター「エマオ」に到着後、ボランティアとしての一日の流れの説明をスタッフより受ける。この日は16時ごろに仙台に着いたので、実働は翌日からになる。 この日に、組織の説明をしていただいた。 |
|||
|
現地の組織 「エマオ」の2階の一室を東北教区が間借りし、「東北教区被災者支援センター」を設置している(四国教区でいえば、松山にある済美会館の一室を四国教区が間借りして活動しているようなかたち)。このセンターにスタッフが詰め、全国からのボランティアワーカーの受入れ・派遣・宿泊をコーディネートしている。組織と役割分担は以下の通り。 トップに仙台川平教会主任担任教師、高田恵嗣牧師(センター長・東北教区常置委員)・・・週に4日センターに詰め、センターの統括、対外的な文書作成・応対などを担当。 以上が仙台の東北教区被災者支援センターの組織。 もう一箇所、石巻にも拠点があり、そこにもスタッフが詰めて、仙台の拠点と連携をとりながらボランティアの受入れ・派遣・宿泊をコーディネートしている。 石巻現地スタッフ3名・・・内勤・料理スタッフがいないため、3人で全てを兼務状態 |
|||
|
10月18日 仙台から車に乗り、岡田・西村は石巻へ向かう。石巻の大通り(大街道)を西から東に走る。この通りにあった瓦礫はすっかり片付けられており、通り沿いにどんどん新しい店が出来つつあった。スタッフによると、「ここに来るたびに新しい店が出来ている」とのこと。 その通りから南に少し下ると、我々の拠点となる家(一軒家を買い取り、リフォームしたもの)がある。石巻は南に海がある。拠点は海から1キロ弱のところにあるため、当然津波が押し寄せた場所の真ん中であり、家だけは残っているがほとんど誰も住んでいない住宅街の中にある。 拠点となる家は二階建てで、女性が二階に、男性が一階に宿泊する。ワークを終え、戻ってきたらスタッフが食事を作り、皆で食べるようになっている。風呂は家の中にあり、また近くに温泉施設もあるので、どちらを利用してもよい。 一軒目のお宅は、ゴミ出しの手伝い。水をかぶった家電製品や鶏小屋など、様々。「ゴミ捨ては市がやってくれないのか」と尋ねると、「市に頼んでも、一ヶ月先になったりする」とのことであった。このお宅も、津波から半年以上壊れた家電やゴミを捨てられず家の中に置いておかなければならなかったのだろう。 午後から二件目のお宅へ。「お宅」といっても、お宅が流された跡地。土台が残されているのみ。その場所の石・ガラス・材木を拾う。人の手で拾えるものだけ拾い、集めておく。後は市の収集に委ねる。 ワークを終えて、夜に石巻の天然温泉に行くが、「温泉」は現在(10月18日)出ていなかった。「来月、温泉が復旧します」と張り紙がされていた。 |
|||
|
10月19日 渡波地区・祝田というところにあるお宅へ。 海に面している地区。石巻の海岸に近いところは地盤沈下しており、このお宅の目の前が海であったが、海抜がほとんどないような感じであった。海に接しているところには土嚢袋が積まれていた。 このお宅での作業は、畑と家の間にブロックを並べ、雨水の浸入を防ぐ、というものであった。更に、家の際にある畑の土を掘り出し、泥水が入らないようにした。 地盤沈下しているため、山に降った雨水が全部、畑を通って家に流れ込んでくるようになったらしい。台風15号の時には床上浸水(80センチ)したそう。この日は岡田・西村の二人で、このお宅を担当。 休憩中、近所の方々のお話を聞かせていただいた。 |
|||
|
10月20日 同じく祝田。前日作業をしたお宅のお向かいの家。 津波は一階を飲み込んだので細かい砂が窓の桟に入り込んでおり、今でも開け閉めするたびにそれが落ちてくる。一枚一枚はずして、高圧洗浄機で桟を洗う作業をした。昼前に新しいボランティアワーカーが合流し、6人での作業。 午後から別のお宅に移動し、敷地の草抜きをする。ここにも津波が届いているので、道具を使いながら掘り返していると土の中からいろんなものが出てきた。オーディオ、車のミラーなど・・・。 被災地の家々は、一見何事もなかったかのように見えるが、外から見ただけではわからない様々な問題を抱えている(例えば、雨が降ったら泥が入ってきたり、窓を開け閉めしたら砂が落ちてきたり)。エマオから派遣されるボランティアたちは、そういうお宅の日常の回復のための小さなお手伝いをさせていただいている。華々しい活動ではないが、そのお宅にとっては非常に大きな意味を持っているはずである。 |
|||
|
二度目のボランティアを終えて 今、仙台の諸教会は援助される側から、援助する側にまわって活動している。しかも、個教会がそれぞれ何かをしているのではなく、仙台の諸教会が少しずつ力を出し合い、協力しあって「東北教区被災者支援センター」を組織・運営している。教会がもっている力は小さいかもしれない。人がたくさんいるわけでもなく、お金がたくさんあるわけでもない。しかし、全国からのボランティアの受入れ・派遣・宿泊のコーディネートを担う、ということによって教会は被災地で大きな役割を果たしているのを見ることができた。現地での受け入れ態勢がしっかりしているからこそ、エマオに何度もやってくるワーカーが多くいるのだろう。 「エマオへの道・四国」に集められた尊い献金により、(岡田は)二度も被災地に行かせていただいた。上記のように、あちらで何か大きな仕事をしてきたわけではない。しかし、そこで以前の街の日常を回復させるために継続して労しているセンターのスタッフや、里帰りするように「また来ました」とエマオを訪れるボランティアワーカーの姿を見て、「小さな働きでも、ずっと続いている」と、励まされ、得がたい体験をさせていただいた。 |
|||
〒791-8031 松山市北斎院町58-3 日本キリスト教団さや教会内
emaoshikoku@gmail.com