9.2 ビームプロセスの特徴
電子ビームやレーザなど非常に細いビーム状の熱源を利用する溶接法は、エネルギ密度が非常に高く、通常のアーク溶接とはまったく異なる溶込み特性を持っています。レーザ溶接を専門に取り扱ってきた人は小物の精密溶接が主流だと思います。私自身は、比較的大型の構造物が専門でしたから、頭の中のイメージがまったく異なっていて、レーザ専門家とは話がかみ合わないことが多くありました。
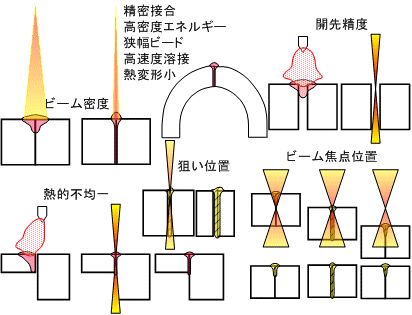
右にビーム溶接プロセスの大まかなポンチ絵を示します。母材に照射された高密度ビームエネルギがどのように熱に変換されるのかは、自分自身良く分かっていません。ある程度ビームが広がって密度が低い場合いは幅広で浅い溶込み、集中していれば不覚細い溶込みと、頭の中で勝手に創造(想像?)しています。電子ビームであれば、ほとんどの電子が母材の中に入り込み、運動エネルギが熱に変換されるというイメージはわいてきます。しかし、レーザ光がどのように金属内に吸収されるのかについては、ほとんど理解できていません。
アークや電子ビームは電磁流体なので、電磁界に大きく影響され、不安定です。アーク溶接では、板厚に大きな差のある部材の溶接では、熱容量に小さい部材温度が上昇し、熱い板の方にアークが集中しがちとなります。高密度ビームはあまりそのような傾向は無く、一気に貫通して突合せ溶接ができます。ただし、非常に細いビームが細い突合せ面を貫通しますから、狙い位置が少し横にそれるとなき別れになり、両者を接合しません。間隙が広い場合には、アークなら何とか両者を溶かすことができます。一方、非常に細いビームは間隙を通り抜けて嶋氏、有効な溶接を実施できなくなります。
ビーム熱源は非常に細いことがその特徴ですが、熱源領域ではそれなりの広さがあります。それをレンズ(光学及び電磁気)で絞って細くしています。ファイバレーザでは星領域で光励起しますから焦点距離の長い細長いレーザとなります。一方、炭酸ガスレーザでは幅広の励起管内で励起したレーザをレンズで絞り込むため、焦点距離の短いレーザ光となります。ビーム焦点位置と母材位置とにより溶け込み特性が変化します。焦点位置が丁度母材表面にあるより、少し母材内部に入ったほうが溶込みは深くなります。母材表面より焦点位置が高い場合には溶込みは浅くなります。
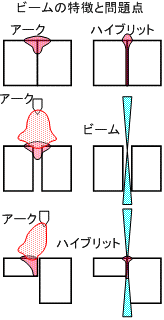
高密度ビームの特徴と問題点を、アークと比較しながら再度右の図に示します。アークは浅く幅広の溶込みとなり、間隙がある程度あっても両者をうまく溶かして融合できます。レーザ単独では間隙を通り抜けてしまいます。アークとレーザとを融合させたハイブリッドにして溶接条件を適切に選定すれば、少々の間隙があってもうまく両方の部材を融合できます。また、部材相互に熱容量の大きな相違が存在しても、アークはレーザにより高温に熱せられた領域に集中する傾向を持つため、うまく溶接条件を選定すれば、良好な溶接結果を得ることができます。
ポンチ絵で説明すると簡単に説明どおりの結果が得られそうに思います。現実はなかなか思う通りには行きません。レーザ自体は高価な機械装置なので、初期の装置にはカメラ系など良質の付属品が多くついていました。システムを少し変更すれば、記録システムとして活用できると思う部分はたくさんありました。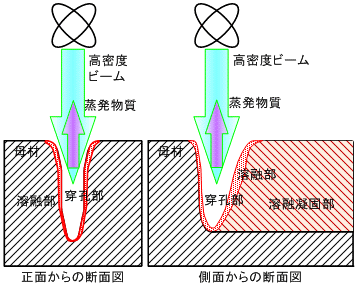 しかし、それらの装置を変更するのは現実問題無理なので、溶接系と観察系とは切り離して独立に利用していました。
しかし、それらの装置を変更するのは現実問題無理なので、溶接系と観察系とは切り離して独立に利用していました。
右の図は、深溶込みではどのような現象が起きているのかについての説明図です。一旦深溶込みが得られると、ビームは金属内部に侵入し、穿孔領域の側面で反射しながら奥深く侵入していくため、穿孔効率が増加しそうだなとは感じます。穿孔領域側面には金属が溶融していると考えます。ビームより後ろの溶融池領域はかなりの厚みで溶融金属が存在します。一般に肺ぶり度も含めたビーム溶接の溶接速度は速いため、上図に示しているように、穿孔部は表面に近いところほど大きく、プルームは溶融池の後退角度に依存してビーム照射軸より後方へと噴出します。このことは前ページで示した映像からも納得できます。
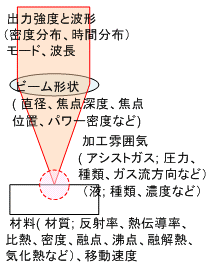
右の図は、ビームプロセスで注意すべき事項の一覧です。ビームの出力強度と波形(ビームの密度分布と、時間分布、モードと波長)は溶接結果に大きく影響します。溶接結果に影響する因子には、ビーム形状(直径、焦点深度、焦点位置、パワー密度など)、加工雰囲気(アシストガスの圧力と流量、ガス流の方向など)と母材材料(材質、反射率、熱伝導率、比熱、融点、沸点、融解熱、気化熱など)及び移動速度(溶接速度)などがあります。
ビーム熱源による熱加工法を簡単にまとめてみます。まず、ビームエネルギが母材に照射されて、母材に熱量の一部が侵入します。光などの場合金属はその多くを反射します。母材内に侵入した光は熱に変換され、金属を溶融します。
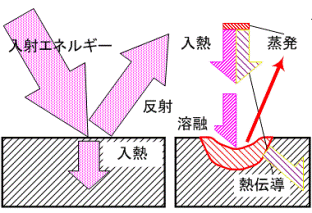
溶融する過程で、溶融金属の一部は蒸発して母材の外部に放出されます。高温になり溶融した金属からは母材の固体側へ熱が伝導して母材全体が均一の温度となるまで、溶接金属の温度は低下します。基礎知識2の章で説明したように、溶融から凝固へと至る過程で母材金属組織は大きく影響を受け、機械的な性質も変化します。
電子ビーム溶接において、母材に衝突した電子の大半が母材内部に取り込まれるのには何の不思議もありません。じっくり考えるとすごく不思議なのですが、そう言うものだと刷り込まれているので、特に不思議とは感じていません。しかし、光の一種であるレーザが金属を溶かして溶接するというのは、未だに不思議でなりません。基礎知識2の章で説明したように、固体表面には、酸化物や吸着された有機系の物質が多く存在しています。太陽光のように通常の密度の光であれば、表面に存在する不純物を積極的に除去することも無く、金属表面で反射されてしまいます。木質系の素材であればある程度の量は材料内に侵入して熱に変換され、ぬくもりのある素材として尊重されます。
金属に光を当てると、金属表面から電子が飛び出してくる現象は光電効果として以下のように説明されています。この説明に対する私の感覚を左のコラムに表明しておきます。
この飛び出してくる電子を光電子といいます。ある振動数以下の光が金属に照射される場合には、光強度が如何に強く(明るく)ても、電子が飛び出る現象は起こりません。その振動数以上の光では、どんなに弱い光を当てても光電子が飛び出しできます。波動のエネルギーは振幅の二乗に比例するので、光を波動とすると、光が強いほど振幅が大きく、エネルギーが大きいはずです。光を波と考えると、この現象が説明できません。光を粒子と考え、粒子1つ1つが振動数に比例するエネルギーのかたまりであるとすると、この現象は説明できます。この粒子を光量子または光子といいます。アインシュタインは光量子仮説による光電効果の解釈でノーベル賞を受賞しました。
金属の自由電子は金属内部で自由に動き回りますが、金属の外に自然に飛び出ることはほとんどありません。自由電子を金属表面から外に取り出すのに必要な仕事、あるいは、エネルギを仕事関数Wといい、金属の種類によって決まった値を持ちます。仕事関数W以上のエネルギを熱の形で与えたとき出てくる電子を熱電子、光によって出てくる電子を光電子といいます。
振動数νの光子が金属表面近くの自由電子に当たると、光子が消滅して、そのエネルギhν(hはプランク定数)をまるごと電子に与えることがあります。この電子の得たエネルギhνが仕事関数w以上の値であれば、光電子として金属の外部に飛び出せます。
以上が光電子効果に関する説明です。実際の固体表面は、酸化物や有機系の吸着物あるいは水分などが密集しています。アルミニウムの表面には安定な酸化皮膜が形成されており、この酸化皮膜は光をよく反射します。レーザ光もよく反射されてしまうため、光を吸収しやすい塗料を塗ってレーザ溶接をする場合もあります。
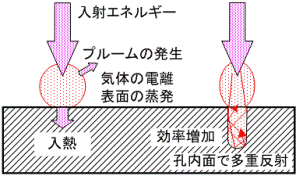
レーザを照射すると、表面に付着している不純物は瞬時に蒸発し、一部は解離・電離します。大多数のレーザ光は金属本体に到達し、初期にはその多くは反射されます。一部は電子を高温度状態に励起し、金属原子も高温になります。一部の電子と元素は表面の外に脱出し、微細なくぼみが生じてきます。表面付着物によるプルーム及び蒸発した金属元素の励起などにより、表面近傍でレーザ光が熱に変換される効率が増加します。また、高温になったレーザ光衝突領域は溶融し、穿孔が始まります。穿孔領域が出現すると、レーザ光の散乱方向の多くは金属内部になり、溶融効率が更に増大し溶接が実現します。
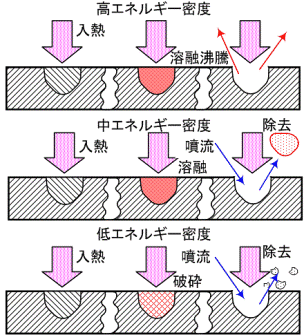 レーザで溶接が可能な理由を、とりあえず以上のように考えて自分を納得させています。金属に照射されるエネルギ密度により、右に示すような3種類の穿孔応答が考えられます。(1)非常にエネルギ密度が高い場合には、金属内部の穿孔領域では、ほとんどの金属が溶融から沸騰の状態になり、プルームとして外部に放出される蒸発除去過程がその極端な場合です。(2)次は、少しエネルギ密度が低くい場合には、金属のほとんどを溶融させますが、外部に溶融金属を放出するだけのエネルギは無く、噴流などにより排出する方法です。(3)最後に、照射された局所的な領域が急激な熱入力により破砕(破断)し、それを噴流などで外部に放出する方法です。
レーザで溶接が可能な理由を、とりあえず以上のように考えて自分を納得させています。金属に照射されるエネルギ密度により、右に示すような3種類の穿孔応答が考えられます。(1)非常にエネルギ密度が高い場合には、金属内部の穿孔領域では、ほとんどの金属が溶融から沸騰の状態になり、プルームとして外部に放出される蒸発除去過程がその極端な場合です。(2)次は、少しエネルギ密度が低くい場合には、金属のほとんどを溶融させますが、外部に溶融金属を放出するだけのエネルギは無く、噴流などにより排出する方法です。(3)最後に、照射された局所的な領域が急激な熱入力により破砕(破断)し、それを噴流などで外部に放出する方法です。
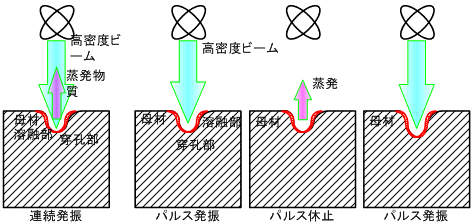 穿孔を行う場合には、連続光を使用すると、深い穿孔領域内部から噴出してくるプルームとレーザ光が干渉する場合があり、一般的にはパルス発振を用いて、レーザ光を部材に瞬間的に照射し蒸発させ、蒸発した成分がプルームとして外部に放出される瞬間はレーザを休止し、一定量が外部に放出された後、同じプロセスを繰り返して穿孔を続行します。
穿孔を行う場合には、連続光を使用すると、深い穿孔領域内部から噴出してくるプルームとレーザ光が干渉する場合があり、一般的にはパルス発振を用いて、レーザ光を部材に瞬間的に照射し蒸発させ、蒸発した成分がプルームとして外部に放出される瞬間はレーザを休止し、一定量が外部に放出された後、同じプロセスを繰り返して穿孔を続行します。
次ページ 2016.04.18作成 2016.04.21改定